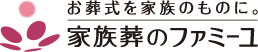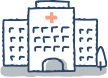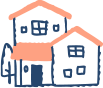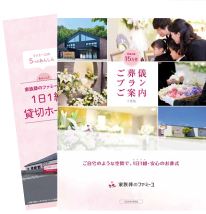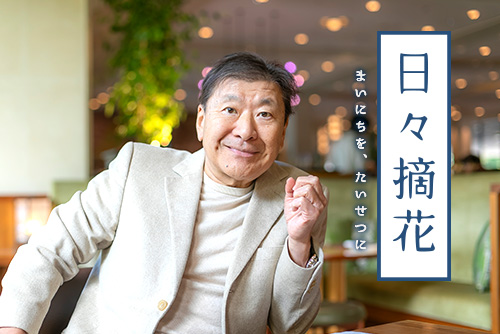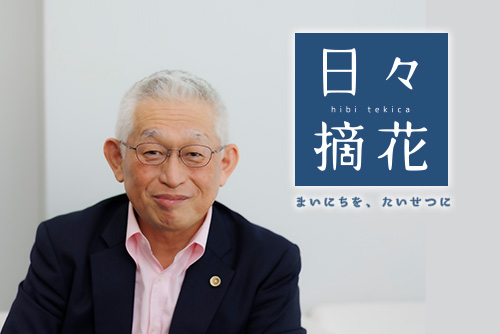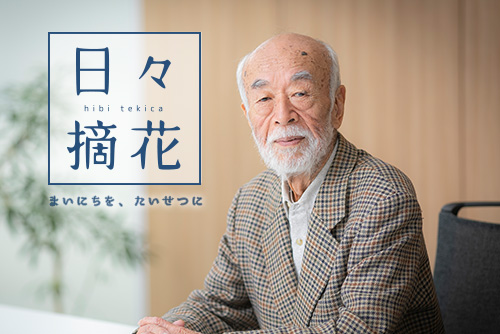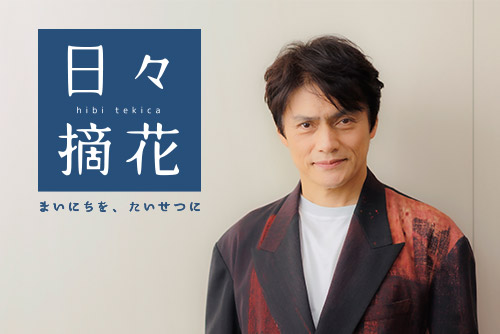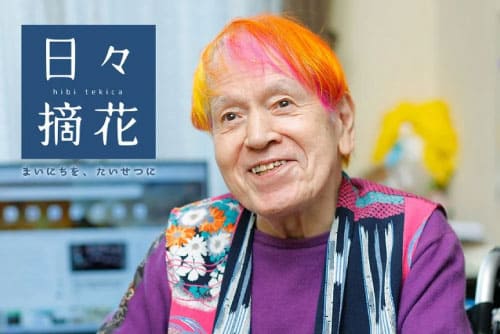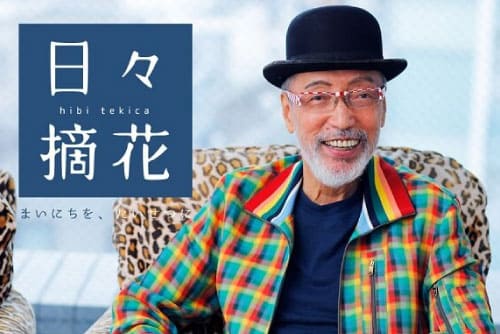白い布をつけて火葬場に向かう!? "神の国" 宮崎県の神聖な葬儀風習
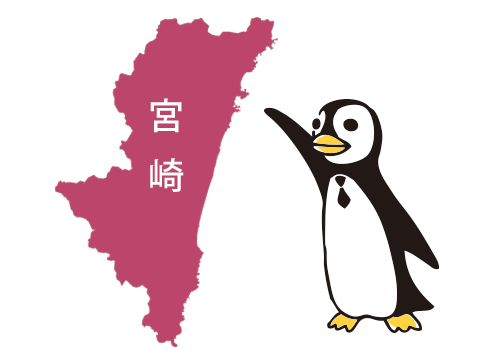
近年、都会で一般的に行われるご葬儀は形式化されていてほとんど代わり映えがありません。しかし、地方ではそれぞれの土地や文化により受け継がれてきた様々な変わった風習が残っています。
"神の国"として有名な宮崎県でも、独特の葬儀風習が受け継がれています。今回はそんな宮崎県の葬儀風習をご紹介します。
御目覚ましとは!?
宮崎県では古くから「御目覚まし」という葬儀風習が伝えられています。一般的に、焼香の後に弔問客に対して食事や飲み物を振舞いながら故人様を偲ぶ「通夜振る舞い」の風習がありますが、宮崎県ではこれを近親者のみで行います。通夜振る舞いの代わりに、地域の習わしとして昔からある隣組などの近隣組織が団子や饅頭などを準備し、ご葬儀の際に参列者に持ち帰っていただく御目覚ましが主流となっています。地域によっては、お菓子の代わりにお米を持ち寄り、おにぎりにして提供するところもあるそうです。
御目覚ましは熊本県が発祥の地と言われ、九州各所で古くからの慣習として代々受け継がれてきました。生前にお世話になった故人様にもう一度目覚めて欲しいという意味や、仏法に目覚めよという意味が語源とされます。
宮崎では、白い布を首にまいて火葬場に向かう
一部の地域では、火葬場へ向かう際、ご家族が「いろ」と呼ばれる白い布を首に巻きつけたり、肩にかけたりする宮崎県特有の風習が残っています。白装束の代わりに白い布を付けて故人様と同じ衣装で見送ることで、「故人様が旅立つまでは同じ格好をしてお見送りしますが、その先はどうかお一人で旅立ってください」という思いが込められているそうです。それに加え、白色は神の使いの動物の象徴とされ、この世とあの世を結んでいる霊界のシンボルであるという意味合いもあります。宮崎県には霊道に繋がっているとされる寺社が数多くあり、白蛇や白ギツネが祀られています。それゆえ、昔から白色は神の証とされているのです。この白い布は、火葬後に厄除けのために数日間、玄関先や近くの木に括りつけられます。
“神の国”ならではのお清めの風習
宮崎県には「不浄払い」と呼ばれる葬儀風習があります。
“神の国”として有名な宮崎県は、天孫降臨の地として名高い高千穂峡を筆頭に、古事記や日本書紀に記されている神が祀られた場所が多く存在します。神道の教えでは、死は非日常的な事が起こった穢れと捉えられます。それゆえ、死という最大の不幸が起こってしまうと、故人様の家の神棚を閉じ、白い半紙で神棚を覆って塞ぎます。さらに、食器などご葬儀に使用した全ての物や場所を柔らかい布で覆って清めます。宮崎県の様々な地域で頻繁に見られるはるか昔から続く習わしです。この不浄払いは、葬儀会場のお清めが済んだ後、すぐさま神官に報告をし、穢れが残っていないか確認をして終了となります。神官が自ら不浄払いを行ってくれるケースもあるようです。宮崎県には歴史に基づいた葬儀風習が今もなお根強く残っています。その中でも神の国としての名残ある霊道的な風習が多くあります。人との繋がりが薄れつつある現代だからこそ、地域の歴史と人を深く結びつける神聖な葬儀風習は、今後も長く受け継がれていくでしょう。
日々摘花(ひびてきか)
~まいにちを、たいせつに~
「日々摘花(ひびてきか)」は、様々な分野の第一線で活躍する方々に、大切な人との別れやその後の日々について自らの体験に基づいたヒントをいただくインタビュー記事です。
このカテゴリの記事をもっと読む
- お悔やみはメールで送っていい!? 友人には?気をつけたいポイントをチェック!
- 香典袋に「新生活」の文字が? 北関東(茨城・栃木・群馬)のご葬儀風習
- お悔やみ欄とはどう違う? 新聞の死亡広告とは
- まずはここから! シンプルイズベストな喪主の挨拶
- 「こんなはずじゃなかった...」ご葬儀にまつわるトラブルを未然に防ぐには?
- 日本に浸透!? 癒しの技術・エンバーミングとは
- 市民葬・区民葬の利用条件は? 仕組みや注意点をチェック!
- 通夜振る舞いのマナー
- 香典の領収書が出る!? 北海道のご葬儀の風習あるある
- 六曜で知る「友引にお葬式はNG」のホントの理由
- 出棺時に棺が回る!? 熊本県の変わったご葬儀風習
- 家族葬だからこそ覚えておきたい「危篤」「臨終」の際のマナー
- ご葬儀に関する手続きは代行できる? 死亡診断書・死亡届 編
- どっちを優先? 結婚式とお葬式の日程が重なったときの対処法
- 「菩提寺」って何? お葬式だけじゃないお寺とのおつきあいとは
- 「家族葬」と知っても慌てないためのポイント3つ
- 弔意が伝わる、供花(きょうか)・供物(くもつ)の贈り方
- お葬式の日程はどう決める? ○○○の確認が必至!?
- ご葬儀で涙の汁を飲む!? 愛知県のお葬式の風習
- 喪家に失礼なく贈る供物のマナー
- 喪主になる前に知っ得、供花のマメ知識
- 家族葬≠密葬!? いろいろあるお葬式のカタチ
- 一日葬(1日葬)で叶える温かい家族葬
- キリスト教葬に参列する際のマナーとタブー
- 誰かに話したくなるキリスト教アレコレ
- 聞いてスッキリ、お布施のイロハ
- 最近よく聞く家族葬のうそホント